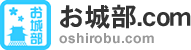松阪城 日本100名城 No.48 【三重県松阪市】ツイート
概要
松坂城(まつさかじょう)は、日本の城。現在は松阪城とも表記される。所在地は三重県松阪市殿町。城跡は松坂城跡(まつさかじょうあと)として国の史跡に指定されている。
城の縄張りは梯郭式平山城である。松阪市の中心地の北部に位置する。阪内川が城北を流れ天然の堀となっている。江戸時代初期には松坂藩の藩庁となっていたが、廃藩後は御三家紀州藩の南伊勢国内17万9千石を統括するために城代が置かれた。
アクセス情報
| 住所 | 三重県松阪市殿町 [Googleマップ] |
|---|---|
| 電話番号 | 0598-23-2381(松阪市歴史民族資料館) 0598-21-0312(本居宣長記念館) |
| - | |
| WEBサイト | - |
| 最寄駅 | JR紀勢本線・近鉄大阪線 松阪駅 徒歩約15分 |
| 最寄IC | 伊勢自動車道 松阪IC 約10分 |
| 駐車場 | 有(無料) |
| その他 交通手段 | 松阪駅から三交バスで「市民病院前」下車徒歩2分 |
| レンタサイクル | - |
施設営業時間
| 開城 | - |
|---|---|
| 閉城 | - |
| 入場 | - |
| 休城日 | 松阪公園内自由 |
施設利用料金
| 大人 | - |
|---|---|
| 高校生 | - |
| 中学生 | - |
| 小学生 | - |
| 幼児・乳児 | - |
| 団体割引 | - |
| その他 | 松阪公園内無料 |
日本100名城スタンプ
設置場所:松阪市歴史民族資料館| 住所 | 三重県松阪市殿町1539 |
|---|---|
| 電話番号 | 0598-23-2381 |
| 営業時間 | (4月~9月) 9:00~16:30 (10月~翌年3月) 9:00~16:00 |
| 定休日 | 月曜日、祝日の翌日、年末年始(12月29日~1月3日) ※展示替えで臨時休館することがあります |
| お城からの距離 | - |
| 料金 | 一般100円 6歳以上18歳以下50円 ※20名様以上の場合は団体割引があります。 |
| 備考 | ※「松阪商人の館」との共通割引入場券もあります。 |
| 住所 | 三重県松阪市殿町1536-7 |
|---|---|
| 電話番号 | 0598-21-0312 |
| 営業時間 | 9:00~16:30 |
| 定休日 | 月曜日・年末年始休館 |
| お城からの距離 | - |
| 料金 | 大人400円 大学生300円 子供(小学生から高校生)200円 ※団体・身障者割引有り |
| 備考 | ※WEBサイト:http://www.norinagakinenkan.com/ |
周辺観光スポット
| 御城番屋敷 | 槙垣と石畳をはさんで静かに息づく歴史空間、ここは江戸末期に紀州藩士が松坂城警護のため移り住んだ武家 屋敷です。 |
|---|---|
| 本居宣長記念館 | 財団法人鈴屋遺蹟保存会が運営管理する登録博物館。江戸時代の国学者・本居宣長の旧宅「鈴屋」を管理して公開し、展示室では『古事記伝』などの自筆稿本類や遺品、自画像などを公開している。 |
| 本居宣長奥墓 | 宣長は、松阪の町、遠くは三河や富士の頂きまでも望めたという山室山を愛し、自らの墓場と決め、遺言を残している。遺言通りに造られた墓の碑文は、宣長の自筆。また背後には、好きだった山桜が植えられている。 |
| 松阪商人の館 | 江戸で紙や木綿を手びろく商いしていた豪商、小津清左衛門の邸宅。 |
| 長谷川邸 | 魚町通りにあるこの邸宅は、江戸時代の木綿問屋「丹波屋」。格子、霧よけ、妻入りの蔵、そしてうだつの上がった屋根など落ちついたたたずまいの中に当時松阪商人の隆盛ぶりがうかがえる。 |
名物・名産
| 松阪肉 | 松阪牛は、優れた資質、行き届いた肥育管理によって日本一の肉牛として認められ、味のすばらしさは「肉の芸術品」として全国、世界から賞賛されている。 |
|---|---|
| 猪肉 | 自然が豊かな松阪では、野生の猪肉を使ったぼたん鍋が食べられるお店も多く、郷土色いっぱいの味が楽しめる。 |
| 松阪赤菜 | 松阪を開府した戦国武将「蒲生氏郷」が伝えたとされるアブラナ科の植物で、江戸時代の国学者、本居宣長も食したという記録が残っている。サラダや漬物に最適。 |
| 松阪木綿 | 松阪商人が江戸で販売した「松阪木綿」は、当時江戸の人々の間で大流行。藍染の色と縞模様は粋な風合いで、今でも人気を得ている。 |
| 松阪万古 | 文久3年(1863)に松阪市下村町に開窯し、後に「松古」として茶器や花器に好まれている。 |
イベント
| 5月下旬 | 松阪撫子どんな花?祭り 松阪撫子献花式をはじめ、なでしこ姫振袖道中など。 |
|---|---|
| 7月下旬 | 松阪祇園まつり 宵宮(土曜日)午後、みこしがくりだし、街を勇壮に練り歩きます。夜店も数多く出店。日曜日は「松阪しょんがい音頭と踊り」「松阪しょんがいソーラン」「松阪鈴おどり」で盛り上がります。 |
| 8月上旬 | 七夕まつり・鈴の音市 当日は平生町から本町までを歩行者天国とし、市民団体等が多くのブースを設け、ナイアガラ花火などいろいろな催事を実施します。 |
| 10月第3日曜日 | 本居宣長 墓前祭 遺言により造られた「奥墓」の墓前で壮厳な墓前祭が行われます。 |
| 11月3日 | 氏郷まつり 商都まつさかの礎を築いた蒲生氏郷公を偲んで開催する氏郷まつりは、蒲生氏郷を中心とした武者行列も行われます。 |
| 11月下旬 | 松阪牛まつり 松阪肉すき焼きの振る舞い、松阪茶業組合におけるお茶の振る舞い、「特産松阪肉・調理実演イベント」、大道芸人によるパフォーマンス、「もちまき」などのおいしい楽しい催しが行われます。 |
ニュース
Loading...